世の中には日々沢山の研究者が日夜研究に勤しみ、数多くの報告が存在しています。
そして、ひとえに医学研究と言ってもマウスや試験管内での結果を主とした基礎研究から実際にヒトを対象とした臨床研究まで様々です。
また、インターネットの発達により、私を含め様々な先生方が医療や論文の解説を行なっていますが、実はご拝読して頂いている皆様に気をつけて頂きたい事があります。
それは、「その論文の内容を、我が子に当てはめて本当に良いの?」と言う点です。
例えば
「(α)の治療を行なったら(or定期的に摂取したら)、(A)と言う疾患が回復(改善)するかもしれない」
と言う論文の紹介があったと仮定します。
その場合、恐らく元の論文では
「(A)と言う集団に、(α)の治療を行なったら80%の患者さんが回復(改善)しました」
などの簡潔な、結果が得られているはずです。
この結果を我が子に当てはめる際に最も注意すべき事の一つは、我が子はこの(A)と言う集団と同じであるか?と言う点です。
例えば、
鶏卵アレルギー患者さん(A)に、定期的に鶏卵摂取(α)を行なったら、80%の患者さんが耐性獲得しました。
と言う論文がもし存在したとします。
それに対して、我が子が鶏卵アレルギー(A)であれば、定期的な鶏卵摂取(α)により、耐性獲得する可能性は高いであろうと言えるでしょう。
一方、我が子が小麦アレルギー(B)だった場合、定期的な鶏卵摂取(α)により、耐性獲得するかと言われると、元の集団(A)と異なる為、効果は期待できないはずだと感覚的に理解できます。
では、
小麦アレルギー(B)である我が子が、定期的なうどん摂取(β)を行なった場合、耐性獲得する可能性は、先程の仮定した論文の結果に準じて効果を期待して良いか?
と質問された場合はいかがでしょうか?
答えは、「No」です。
集団(A)と介入(α)の関係性は、A-α間でのみで確認されています。
その為
集団(B)と介入(β)には、また別の研究(論文)で結果を確認する必要があります。
いやいや、鶏卵(A)で得られた結果なんだから、小麦(B)でも恐らく同様の結果が得られるだろうから、介入(β)をやってみたら良いじゃないか⁈
と言う意見もあるかもしれません。
勿論、当たって砕けろ的に挑戦した結果、集団(A)と介入(α)と同等の結果が得られる可能性はあります。
一方で、集団(A)と介入(α)より低い結果しか得られない可能性や、実は合併症(アナフィラキシー)の可能性が高くなるといった、マイナスの結果になるかもしれません。
つまり、集団(B)と介入(β)の関係は、集団(A)と介入(α)の関係からは「分からない」としか言いようがないのです。
より具体的に
成育医療センターが発表した世界的に有名な「鶏卵アレルギー予防研究」
(Two-step egg introduction for prevention of egg allergy in high-risk infants with eczema (PETIT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trialを用いて、考えてみたいと思います。
Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):276-286.
この研究の介入方法は、生後6ヶ月より加熱全卵粉末50mg(全卵約0.2g相当)を摂取開始し、生後9ヶ月、12ヶ月時に負荷試験を行い、鶏卵摂取量を増量していくと言うものでした。
では、「この介入方法を生後6ヶ月で鶏卵アレルギーの我が子に導入して良いか?」
と質問された場合はいかがでしょうか?
答えは勿論、「No」です。
なぜならこの研究は予防研究であり、対象となる集団(A)は、鶏卵アレルギーをまだ発症していない乳児(湿疹あり)だからです。
その為、既に鶏卵アレルギーを発症している(B)場合、上記の介入(α)を行なっても同様の結果が得られる保証はなく、逆に介入により強いアレルギー症状を認める可能性もあります。
このように一見当てはめても良さそうな研究結果も、本当に我が子に当てはめて良いかと言う点には慎重さが必要です。
もし、インターネット上で気になる論文の紹介などを見つけたら、お子さんに適用して(当てはめて)良いかに関して、主治医の先生と一度内容を確認・相談される事をお勧めします。
本日は以上となります。
近年インターネットを通じて、様々な情報を手にいれる事が出来るようになりましたが、その情報をどう使ったら良いかまでは教えてくれません。
これからも、ブログやツイッターを通じて一緒に学んでいけると嬉しいなと思います。
では、また次の記事にてお会いしましょう。
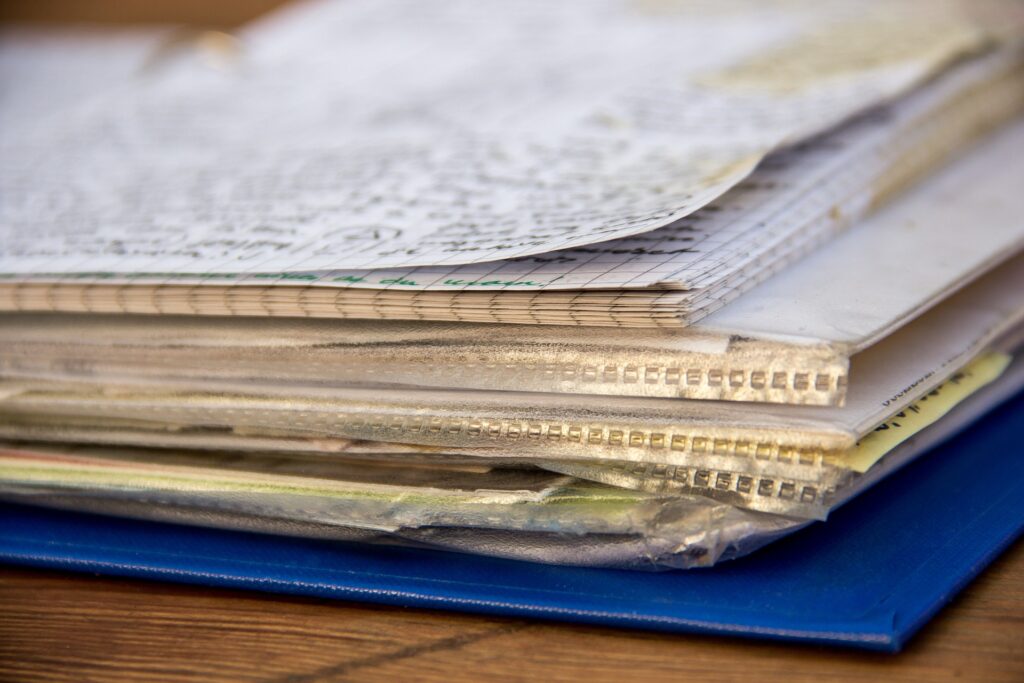


コメント